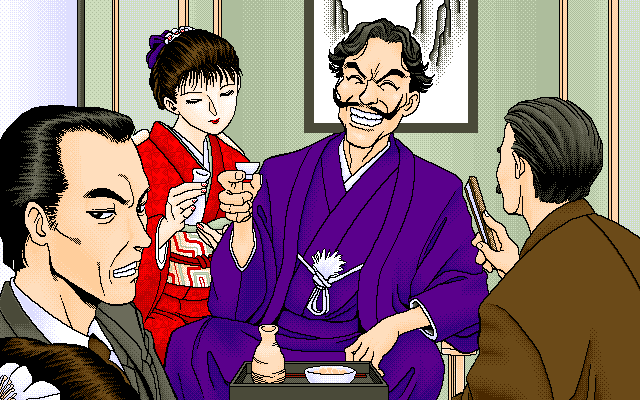
Illustration by Kunio_Aoki

act.4-1;探偵は再び訪れる
「あの……いいですか?」
「あ、はい……西石さん!?」
スリムな体にふわっとした栗色の髪。それは、ルフィー西石だった。
恭子は少し表情を固くした。
ルフィーは、微笑みを浮かべて言った。
「ア・ハッピー・ニュー・イヤー。そして、お久しぶりです」
「西石さん……そんな、なぜここに? だって、まだアフリカじゃないんですか?」
恭子は戸惑った。昨年の暮れに電話を入れたときには、ルフィーはパリ・ダカール・ラリーに出場していると言われた。そして、今日の昼のニュースでは、ルフィーのチームは依然快調にアフリカの大地を走っていると告げていたからだ。
ルフィーは少し困ったような目をした。
「恭子さん、あなたにお詫びするために僕の秘密をお教えしましょう。今、パリ・ダカに出走しているのは僕自身ではありません。僕の東京での現場不在証明……アリバイ工作のために調達した替え玉です」
「そう……お仕事たいへんなんですね」
恭子はそっけなくルフィーをあしらった。
「食事の約束をしながら、期日も告げる事なく放り出してしまってもうしわけありません。今日はその約束を果たさせていただこうと思いまして」
「いえ、けっこうです。わたし、一度だけしかお会いしたことのない方に食事に誘っていただくわけにはいきませんから」
恭子は店の奥から小箱を持って戻ってきた。
「それから、これもお返しします」
それは、薔薇をあしらった小さなブローチだった。
「あなたにここまでしていただけるようなことをした覚えはありませんもの」
帰省の間中ずっとルフィーの一件ばかりを考えていた恭子だったが、彼を一人の客として以上に特別な存在としては扱わないことに決めたのだった。ルフィーはプリンセスに訪れた客の一人であって、それ以上でもそれ以下でもない。
昨年のクリスマスに恭子に贈ったはずの品を前に、ルフィーは懇願するように言った。
「それは……あなたに差し上げたものです。あなたに身につけてもらうのがもっとも似つかわしいものであり、僕の手元にあったとしても何の輝きも見せないものです」
「でも……」
ルフィーは小箱からブローチを取り出すと、恭子の瞳をじっと見据えたまま、白衣の胸にブローチをつけた。
「あなたを飾るためにしつらえられ、そしてあなたに贈られたものなのです。どうか あなたの手元においてください」
まるでドラマのようだった。銀幕の世界にいるようだった。たとえ恋人と二人っきりになれたとしても、日本人ではこのセリフは出ないだろう。さすがシェークスピアとホームズの国の紳士だけある。
あまりにドラマチックすぎる一幕を体験した恭子は、ルフィーの次の言葉が発せられるまでの間、遠い目をしていた。
「かけてもよろしいでしょうか?」
「え、ええ。ど、どうぞ」
かすかに頬を桃色に染めてどぎまぎしていた恭子は、ルフィーにチェアを勧めた。
コートを受け取り、タオルと白布をかけてルフィーの髪を丹念に梳きはじめる。髪に櫛を入れる恭子の表情は先ほどまでとは打って変わって、その道のプロのものに変貌している。
鏡に映る恭子をじっと見ながら、ルフィーはこともなげに喋り出した。
「初めてお会いした時に、根戸氏の話をしたのを憶えておいででしょうか」
憶えている。
社会派番組やヤラセ特番、最近では冒険番組ディレクターとして密林探検番組を企画中と喧伝している、情報詐欺師・根戸宏が携えている情報のこと。それを知るだけで、世界中の諜報機関から付け狙われてしまうほどの極秘情報を、根戸宏が持っている、という話。
でも本当かしら?
ルフィーは、髪をくしけずる恭子の指先からその思いをくみ取ったように続けた。
「……何しろあの根戸氏絡みの話ですから、信じられないのは無理もない話です。しかし、彼が何かを知っているらしいのはまぎれもない事実です。そして、それが彼を危険にさらしていることも」
「そうなんですか。大変ですね」
「そう、大変です。彼は去年だけで4回ほど交通事故にあいかけている。いずれも加害者の正体は不明です。何しろ、行動の足取りをなかなかつかませてくれない人なので、僕の調べていない場所でもいろいろな目にあっていると見ていいでしょう」
洗面台を引出し、洗髪する。しばし会話が中断する。
乾いたタオルで雫を拭いさられた後、ルフィーは続けた。
「このままでは彼は、いつか命を落とすでしょう。そこで、僕は彼を救いたいんですよ。しかし、彼が知っている情報が何なのかを知らない限り、手の打ちようがない。誰が彼を狙っているのか、ではなく、彼の何を狙っているのかがわからないと。しかし、僕では彼に近づけないんです」
「なぜですか?」
「初めてあなたとお会いしたときのことを憶えていらっしゃいますか? あなたは、初対面の僕を見て、僕がルフィー西石であることをためらいなく言い当てた。僕は、探偵としては面が割れすぎているんですよ。以前の僕なら多少ならどうにでもなった。顔が知られているからどうのっていうほどの大物でもないですしね。しかし、今は少々状況が変わってきた」
熱い蒸しタオルをルフィーの顔に乗せる。一瞬、言葉が途切れる。
「……去年、軍事学部とちょっともめましてね。僕と根戸氏の親密な接触が軍事学部に知れると、根戸氏に新たな危機が及ぶ可能性もあるのです。だから、ルフィー西石ではない、別の人間が彼に接触しなければならない。そのためにルフィー西石はパリ・ダカール・ラリーに出走していて、東京人工群島にはいないことにしてあったのですよ」
「そうだったんですか……」
「あなたに、真実をお知らせできなかったことは本当に申し訳ないと思っています。これで許していただければいいのですが……」
「許すだなんてそんな……でも、これであなたが東京にいることが知れてしまっては、あなたのお仕事に支障が出るのではありませんか?」
「そうですね……。できれば誰か面の割れていない人物が協力してくれればありがたい。その人物が根戸氏の元へ行って、彼の真意を聞き出してくれれば……」
恭子はルフィーから白布を剥すとぱたぱたとはたいて髪を払った。
「まるで007みたいですね」
「ええ、まったく。ジェームズ・ボンドみたいなものですね。でも、今度の依頼人は国やなんかじゃなく……これは極秘なんですが、根戸氏についての依頼人は彼の恋人からのものなんです。彼の身を案じて、自分に何か出来ることはないか、何が彼を危険に晒しているのかを知りたいと言われましてね」
「根戸さんの恋人?」
「そう、鵜飼くーみん嬢です」
「鵜飼さんが? 根戸さんの?」
「これ、くれぐれも内緒ですよ」
ルフィーは念を押して椅子から立ち上がった。恭子はルフィーのシャツを手箒で払いながら言った。
「……西石さん、その大役、あたしにできるかしら?」
「え?」
「根戸さんから、その大事な情報というのを聞き出せばいいのでしょう?」
「ちょ、ちょっと待ってください。あなたをそんな危ない目に会わせるわけには」
「あなたの知っている大事な秘密をこんなに知ってしまったんだもの。わたしとあなたはもう共犯なのではないかしら? それに、わたしの電話で、あなたのお仕事の予定を狂わせてしまったのだとしたら、その埋め合せをしなくちゃね」
ルフィーは、そのブルーの瞳で恭子をじっと見据えた。
「わかりました。では、あなたに危険が及ばないよう、僕に守らせてください。あなたにだけは何者にも絶対に手出しをさせませんから」
「わたしなら大丈夫。でも、その言葉だけでも嬉しいわ。ありがとう」
恭子のブローチにそっと手を添えて、ルフィーは言った。
「このブローチを、僕の代わりに持っていってください。お守りだと思ってください。効果はてきめんですよ」
恭子はほんの少しわくわくしていた。ロマンチックなラブシーンに続いてスリルに満ちた活劇シーンが脳裏をよぎる。他の誰でもない。わたしが主役なのだ。
「心配ならいらないわ。銀幕のヒロインは必ず成功するって決まっているもの」
新年3日に根戸宏のマンションで始まった新年会で、飛鳥龍児が憶えている自分の最後のセリフである。
その後、何があったのかは定かではないが、4ケース用意されていたビールと、例によって例のごとく根戸の隣の部屋の住人から根戸の不在の内に差入れられていた、総量がtにも及ぶのではないかと思われるほど膨大な量のおせち料理が消えていたことから解るのは、ジェーン壱代寺はもう帰った後であるということである。
酒と食い物と宴会のある場所には必ず現れ、宴が終わるまで一人で喋りまくった挙げ句に、酒と食い物がなくなるまで飲み食いし尽くしていく。ジェーン壱代寺はそういう女である。
飛鳥自身、寝ても覚めても飲み続けの生活を送ってきたらしい。途中、幾日か記憶は抜けているが、よく飲んだなあという意識だけは心の何処かに残っている。
飛鳥は、自分同様部屋の何処かでマグロになっていると思われる家主の根戸宏を探した。しかし、彼の姿は居間には見あたらない。
「ねとさん?」
飲み過ぎと眠りすぎで足腰が立たない。声も出ない。
「ほーい、おはよう」
根戸の寝室兼書斎となっている奥の部屋から、いつもの軽快な声が返ってきた。ジェーンほどの飲みっぷりではないとはいえ、確か根戸も飛鳥と同じくらいには飲んでいたはずである。なるほど、鉄人だ。
飛鳥は感心しながら敬愛する根戸の書斎へ身体を引きずっていった。
「おはようございますぅ。ええと、今日は?」
「今日は1月11日。鏡開きの日。時間は午後の3時過ぎといったところかな」
「ではあれから一週間以上も過ぎていたんですか……?」
「そう。今週一週間分のトピックをピックアップしてあるけど読む? 群島プロムナードのCVIEW公開以外に、特に目だったニュースはないみたいだけどね。今の所」
「いつのまに仕事に復帰していたんですか。僕がマグロになっていた間にですか?」
飛鳥はいぶかしんだ。しかし、根戸はこともなげにいった。
「いや、最低限、ニュースは毎日チェックはしてたんだよ。幸いにしてというべきか、残念ながらというべきかは知らないが、この一週間ネタになるような大事件は世間にも自分にも起こらなかった。故に、安心して酒宴に身を委ねられていたわけだ」
「なるほど……そのたゆまぬ努力と敏感なアンテナが、ジャーナリストには必要なわけですね」
「お。わかってきたね。だからといって、ただ漫然と調べているだけではだめだ。テーマを定め、特定の目的を持ち、それに併せて推論し仮説を立てて、仮説を立証するために取材するんだ!」
「はい、コーチ!!」
昨年末、ビッグサイトでの取材の後から、根戸と飛鳥の関係は師弟関係とも言うべき間柄となりつつあった。取材の仕方、着眼点など、根戸はことある事に自分のノウハウを飛鳥に教え、センセーショナルな騒動の盛り上げ方を教授した。
元来が生真面目で、そして生まれついて根戸と同じ気質を持ち合わせていた飛鳥の上達ぶり……その根戸化ぶりには目をみはるものがあった。
「これまで繰り返してきたように、僕の統一シリーズ・テーマは『群島を知る』もしくは『群島の謎を解く』だが、これを先の方法論に当てはめて考えたとき、『群島は集団の無意識が作ったものではなく、誰かが意図的に作ったものだ』という仮説の上に立って取材が進められている。人工群島を作りだそうとした人物は誰だと思う?」
「……人工群島の開発の発端となった1993年の海底隆起の後、事業開発推進の旗頭となったのは、当時の都知事鈴木俊一。この人物は確か、1964年の東京オリンピック開催のとき東京都副知事を務め、その頭角を表わした実力派……でしたね」
「大阪万博にも関係していたと思う。とにかく、元来が『都市開発』という思想に根ざしてきた人で、海底隆起という東京港の不幸を、いち早く洋上都市開発の幸運なファクターにすり替えてしまったあたりの手腕は評価するに値する。彼の不幸は高齢だったこと、かな。東京人工群島という巨大事業を進めるには歳をとりすぎていた。だから、志し半ばにして倒れた時は無念だったろうな」
「では、人工群島は鈴木氏が意図的に作り出したものだと……?」
「いや、それは早計にすぎる。鈴木氏はあくまでも開発の発端を作り、現在の群島区北にあたり、群島全域のモデルケースとなっていく晴海・有明のテレポートシティを実現させたに過ぎない。もちろん、その功績は多大だが、その後の『東京人工群島』という巨大な計画が実現していこうとしている現在、彼はもうこの世の人ではない。鈴木氏の後に現われた、カリスマと実務力を兼ね備えた施政家たちは、彼の影響を多分に受けていると思っていいだろう。そういう意味においては、鈴木俊一という人は都庁・行政府における洋上都市開発の思想の源流にあり、この計画における思想的先駆者……と見るのが妥当なんじゃないかと思う」
根戸宏は、これまで集めた情報を個人用としては巨大すぎる光ディスク・メモリに注ぎ込んでいた。しかし、このメモリに集められている情報は、あくまでも加工前のデータに過ぎない。調べようと思えば、特別な技能や職権なしにいくらでも知ることができるありふれたデータでしかない。特別な技能を持つデータ・エージェントが、仮にプロムナード上にある根戸の情報領域を走査したとしても、何処ででも知ることのできる当り前のデータしか入手することはできなかっただろうし、根戸の部屋に侵入して個人用メモリを走査したとしても、答えは同じだろう。
微かな作動音をあげて、読み込まれたデータがモニタに並ぶ。
「この種の計画を実現するためには、意志、人、金が揃わないとなかなかうまくいくもんじゃないんだなぁ。意志というのは目的に全体を引っ張っていく思想的指導者。発端部分での思想的指導者というのが鈴木氏なんじゃないかな。人は目的を達成するに足る実力を持った人材。鈴木氏の4期以上に渡る都政の間に、彼の門弟とも言える人材が育ったことは、人工群島にとって非常にラッキーだったと言っていいだろう。しかし……問題となるのは金だ」
「東京都って金持ちだったんでしょう?」
「確かに、当時のほとんどの道府県が国庫からの援助なしには地方行政ができず『3割自治』となじられていた時代に、都内の都民税や法人税などの収益だけで『7割自治』を行い、その貯金で都庁移転やテレポートシティ建設にこぎつけたのを見れば、なるほど金持ちに見えるね。
でも、こういった都市は、官民一体となって進められなければ、そうそう実現できるもんじゃない。確かに東京都が音頭をとって進めているが、如何に東京都でも資金のすべてを肩代りするだけの財力はあるはずないだろう。
さて、君が都知事だったら、どうしたらいいと思う? 計画を諦めず、縮小せず、実現させるための手段を講じたとして考えてみたまえ」
「そうですね……都市機能を第三セクター化して、官民合同運営のものを増やすとか、都市開発への参入が産業界にプラスになることを示して、資本介入だけでなく事業介入させるとか?」
「うん。行政レベルとしてはそんなもんだろう。他にも方法はあるけど、今は割愛ね。ここで金を出しつつ事業として人工群島に介入してくるだろうと思われるのは、当然ながら企業なわけだ。人工群島の基礎事業として、オフィス・住宅の提供を基幹に土木建設、各種交通網の整備敷設、電信電話映話などの通信事業の整備が必要不可欠なわけ」
「これに都市に付帯する各種流通企業が潜り込んできて、東京拡張版のできあがりってわけですね。当時、東京一極集中への改善策としても論じられてきた遷都論への、東京のひとつの抵抗でもある。『東京はまだ満杯じゃないぞ』と。東京というブランドは、まだまだ商品価値を高める魔法の呪文だったし、企業側としても長年培われてきた首都=東京=中央=標準のイメージを一朝一夕に捨てて、新しい首都のイメージを育て直すリスクよりは、東京の器を広げる側を選んで東京の抵抗に協力したというわけですか」
だんだんと飛鳥の口調が根戸のそれに似てきた。が、本人はそれと気づく様子もない。どこから見つけだしたのか、奇蹟的にジェーン壱代寺の魔の手から逃れたアーリータイムスを、根戸と自分のグラスに注いで、ぐっとあおぐ。
「でも、まだヘンですね」
「どこがおかしいと思う?」
「いや……なんだか、動機付けが弱いような気がして。確かに儲け話ではあるんですけど、なんていうんでしょうか……この場合、都知事サイドに理想家がいたわけですよね。理想というのはコトを進める上で非常にウェイトの大きいファクターではあります。でも普通、財界人とか経済人ってのは理想だけでは動かないでしょ? だから、何か大きな儲けがあるとわかっていても二の足を踏んでいそうな……。元々二次大戦後に成長した日本企業というのは、競争力の秀逸さで大きくなってきたわけで、何か競争を促す、もしくは競争に発展する可能性を含んだ別の目的があったからこそ、群島が今のように極端に発展したんじゃないんでしょうか。その目的がなんだかはっきりしないんだけど……それに付随する競争で企業が潤えると考えているのは確かだと思うし……また、企業に対して、競争を煽っている存在があるような気がしますねぇ」
飛鳥はまとまらない考えを必死にまとめようと苦心惨憺している様子だった。逸る心を抑えようと、グラスに残ったアーリーを喉の奥に流し込む。飲むほどに上長になるタイプのようだ。
「ここで年越しとなった『バイオスフィアと人工群島の甘い関係』が現われてくるわけだね。僕は、東京人工群島はバイオスフィア、引いては宇宙開発を産業の域に推し進めるために、意図的に作られた物だと思っている。問題は誰がその糸を引いているかなんだけど、有力な候補としては、まず」
と、そこへチャイムが鳴り響いた。
根戸はグラスをおいて立ち上がり、居間に散乱している物をひょいひょいと跨いで玄関へたどり着いた。
「……まず、来客を片付けよう」
根戸は少し身構えた。最近、自分の留守に部屋を訪れたと思われる人物が2種類いることに気づいていたからだ。それは明らかに悪意を持った侵入者と、悪意を持っているのかもしれない侵入者である。
前者は、根戸のデータを物理的に漁りにくるデータ・エージェントである。室内はまったく荒されなかった(いや、元々荒れているので、違いがわかりにくかっただけかもしれない)が、部屋主である根戸自身には、侵入者の痕跡がはっきりと見て取れた。彼らはそのほかの物には一切目もくれず、根戸の留守を狙ってデータを漁りまくっていったようだ。しかし、何も見つけられないだろうことは判然としているため、根戸は前者には対して警戒心を抱いてはいなかった。
問題は後者であった。
昨年、引っ越してきて以来、蕎麦、米、そしてこの正月にはおせち料理と、根戸の留守を狙っては膨大な量の食糧を置いていく隣人……基礎工学部農業工学科・白葉透教授、その人である。
「もし白葉教授だったら、真意の程を確かめる必要がある」
「でも、別に弊害はないんでしょ? むしろ、食べ物を置いていってくれるというのは、善意の表れのようにも思いますが」
「善意だって? あれは食物テロといってもいいような仕打ちだぞ。僕は認めん。あれは断じて善意などではない。悪意に満ちた行為だ。
だいたい何処の世界に生蕎麦をむき身で置いていく奴がおる。何処の世界に500キロの米を俵で置いていく奴がおる」
「現にいるじゃないですか。隣に」
「いや、これは謀略だ。何かの謀略に違いない。白葉透は、僕になんらかの強圧的メッセージを送っているのかもしれない。いや、そうに違いない」
「そうですかねぇ……」
「これまでの所、データ・エージェントは僕の留守だけを狙ってきている。彼らは僕と接触する必要がないと思っているからだ。しかし、今このドアの向こうにいるのは、きっとデータ・エージェントではない。白葉透が巨大な大根の束を抱え、人参とトマトを担いで、含みのあるにこやかな顔で立っていやがるに違いないんだ! 白葉! 今日こそ、貴様の真意を白日の元にさらしてやる!」
根戸はドアを開けた。
「あの、根戸さんのおたくはこちらでよろしいんでしょうか。わたし、平山といいます」
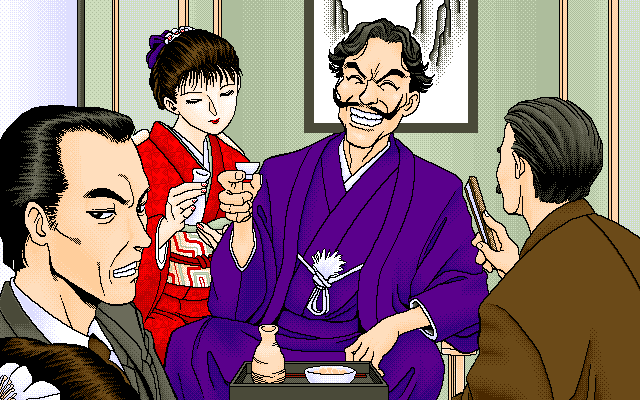
「三宅さん。昨年はご苦労さまでした。ま、ひとつ」
「うはははは、いや、しかしこの酒はうまい。たまらん」
「うはははは。この吟醸酒『夜明け前』は、昨年うちの講座が満を辞して発表した幻の米『群島の夜明け』の兄弟籾を50%精米し、米どころ新潟から招いた杜氏が仕込んだものでしてな」
「ほほう、この軽い飲み口がもうたまらんね。さすが農工学科、いい米だ。しかし、日本酒と言えば水が命だろう。水はいったいどうやって手にいれたのかね」
「うはははは。そこはそれ。我が農工学科のダウジング技術と、三宅総研材料工学研究室の浄水膜の粋を極めた精水プラントの成果ですな。いや、この酒の旨さは我が農工学科だけでなく三宅さんの御力でもあるわけですな。うは。うはははは」
「そうかね。うむ、やはり酒は水が命。水は生命の源というからな。いやぁ、身体中に生命が染み渡るわい」
「いやいや、もう一献いかがですかな」
「いやあ、そうかね? うはははは。これで酌をしてくれるコでもいればなおよいが」
「そうおっしゃると思って、隣室に用意させておきました」ぱんぱん
「教授☆ よろしゅうお願いしますぇ☆」
「おお! このどことなく京都弁な響き、そして襖をすっと開いて三つ指をつくこの儀式めいた優雅な動き。いやぁ、3LDKのマンションでこういった風情を楽しめるとは思わなかった。白葉くん、株を上げたな、株を」
「いやぁ、滅相もない。お代官様には今後も御贔屓にしていただきたく、存じ上げる次第で……」
白葉透は額を畳にすり付けるように深々とさげ、三宅教授を上目遣いにちらりと盗み見た。
隣席ですでに数人の女の子と戯れていた基礎工学部生物工学科・金居祐三教授は言った。
「どうでもいいが、お代官様ごっこはもう飽きた」
「金居! まったく付き合いの悪い奴だな。自分がいい思いをしたら他の者はどうでもいいという、お前のその根性が気にいらんのだ。そうだ、お前は昔から嫌な奴だったな」
「てやんでえ! てめえに言われる筋合いはねえ! だいたい、てめえはいつからそんなに偉くなったんだ、ああ? 三宅! なんだったら今すぐ勝負をつけてやろうじゃねえか、勝負を!」
「まぁまぁ、三宅さんも金居さんも、今日はめでたい新年の宴の席じゃありませんか。えーっとね、ひとつここはこの不肖白葉透に免じて、どちら様も、ねっ? ねっ?」
白葉教授は3つ年上の三宅教授と金居教授のなじりあいをうまく丸めこんだ。何しろこの二人の喧嘩癖は今に始まったことではない。三宅・金居・白葉の三人が、某国立大学の哲学科で出会ったときから、もう30年近くも続いている年中行事のようなものだ。なだめる白葉ももうお茶の子さいさいである。
学生時代、3年休学して遊び歩いていた三宅と金居、そして現役で入学した白葉の三人は「哲学では飯が食えん!」という同じ答えに行き着いた。そうして、三宅教授は機械工学・関節制御、電子工学などを網羅し工学系全般へ、金居教授は生物学を経て遺伝子工学へ、白葉教授は実家北海道札幌市の農業に尽くすため農業工学の道へそれぞれ歩んでいったのである。
もし、宴席でこの3人に会ったら、どこにでもいる飲んだくれのおっさん以外には見えないかもしれないが、彼らは都立東京洋上大学の歴とした教授であり、それぞれバイオスフィア計画の主幹の一人なのである。
たとえ信じられなくてもいいから、ここはひとつ信じてほしい。
バイオスフィア計画は、東京都立洋上大学に集められたその筋の権威と、職人的研究者たちによって推し進められていた。
教授クラスの研究者は数千〜万の単位でバイオスフィア関連の研究に勤しんでいた。
優秀な人材を広く様々なジャンルに振り分けて個々の研究を進めさせるより、ひとつのジャンルに集中的に優秀な人材をつぎ込み、一気にブレイク・スルーを狙うという意図に基づいた人材戦略である。
通常、こういった総合的なプロジェクトは、ひとつひとつ技術の壁や理論を実用化し、新しい技術がクリアになるたびにそれに基づいて、次ステップ以降の研究課題を設置する。しかし、それでは遅すぎるのである。
高度に細分化専門化された学術体系の泣き所は、汎用性・応用性の低下にある。ある総合的な目標をこれまで以上に短期間で達成するためには、複数のジャンル、例えばメカニクス、マテリアル、エレクトロニクス、バイオといったジャンルの専門家が必要である。
しかしそれ以上に必要なのは、それら直接関連のないジャンルに対して、総合的にプロデュースし、目指す総合的な目的に沿うように個々に分立する研究をディレクションする、そういった「コンセプチャー」もしくは「管理職的研究者」であった。管理職的研究者は、あらゆるジャンルの学問に広く精通し、博識であることが望まれた。
コンセプチャーもしくは管理職的研究者。耳慣れない呼び名である。
通常の研究者は、ある仮説を立証するのに理論を用いる。そうして作られた理論を、さらに別の技術者が応用を重ねて、やっと「機能を持った製品」にたどり着く。
これに対して、彼らコンセプチャーは「こんなものが作りたい!」「あんなものがあったら便利だ!」というコンセプトもしくは最終形態を思いつくところから理論の体系付けと実際の理論応用技術を同時進行で進める。
その作業形態は、特定のデザインを先行して決め、後からデザインに納まるように部品を製造したという20世紀末の商品化技術にも似ているが、もっとストレートに思い浮かぶのは、「マッド・サイエンティストの研究所」であろう。過去のマッド・サイエンティストは、一人であるがために総合的知識運用を自ら行なっていた。それが、先駆的発明やブレイク・スルーを自然に促す結果を招いたのである。そうして彼らが作りだした、理論の解明よりも現物が先行している発明品は、その直後の科学を大きく進歩させた。
先端研究者ではなく一発明家のひらめきで開発されてしまった発明品と言えば、日本のエジソン・ドクター仲松によるフロッピー・ディスクの発明やE・テラーによる水爆の発明などがあるが、フロッピー・ディスクの発明が、それまでのオープンリール・テープによる記憶媒体を大きく進歩させた経緯を思えば、マッドサイエンティストもしくは発明家による、ブレイク・スルーが如何に重要かつ偉大なものかがわかるというものだ。
この人事戦略では、総合的な見地から頂点に立つマッド・サイエンティスト……いや、コンセプチャーの存在なくしては語れない。
そのコンセプチャーとして、バイオスフィア計画の全研究の方向付けを行なっているのが、三宅準一郎教授その人であり、その元でそれぞれ生物全般・植物全般の総括を手伝う立場にあるのが金居教授と白葉教授なのである。
「で、どうなんだ。工場野菜の実効生産力の方は」
「えーっとね、光源の確保さえできれば、食い物には困らないはずですな。ただ、被験者の住環境における心理的欲求を満たすためにですな」
「白葉君、分かりやすく」
「まぁ、多少広くて、木もいっぱいあった方が気が楽になっていいんじゃないかと」
金居教授は碗に注いだ『夜明け前』をぐいとあおって言った。
「先々はともかく、現段階でそんなだだっぴろい空間を宇宙に持ち出せるか。脱地球、宇宙植民という概念はいいとして、宇宙が人間に向かないからって、地球と同じ環境を持ちだそうという、そのゆりかごにしがみつこうとする後向きな根性がいかんのだ。閉鎖生態系をもう一歩進めて、人間の中に閉鎖した生態サイクルを作ってしまうのがいちばん理想的に決ってるじゃねぇか」
「じゃあ、何か。おめぇは『マン・プラス』や『カンガルー・ノート』のスネからかいわれ大根男みたいな、閉じた生態系を人間の身体の中に作れっちゅうとるんかよ」
「機能的でいいだろう。スペースもくわず、大がかりに地球環境を再生して持ち出す必要もない。これこそ……」
「このアホタレが。人間を改造してどうする。人間は道具を発達させた機械というオプションを扱うことによって無限の進化を約束された高貴な種だぞ。過渡期的に単体を改造するならともかく、長期に渡って人間という種そのものを改造し続けたら、それはすでに人間ではなくなっちまうだろうが。人間はあくまで生態系のユニットにしなければいかん。宇宙環境と人間との間に緩衝となる部分を作らんと、環境の激変に弱くなるだろうがよ」
「ま、ま、ま。お二人とも、ま、御一献」
白葉教授はつかみあう三宅教授と金居教授を引きはがし、碗に酒を注いだ。
「わたしとしても人間が野菜さんたちと同じように光合成で生きていけたら、なんと素晴らしいことだろうと思います。が、いかんせん今の技術では、太陽の光を生命に替える方法が手に入りません。というわけで、まずはできることから始めましょうって約束だったじゃないですか。えーっとね、そういうことでどうでしょう。ま、もっともこういう研究は地べたで騒いだってどうにもなりゃしないわけで……あー、早く学生押し込めたバイオスフィア・プラントを宇宙空間に浮かべたいもんですなぁ」
近年稀に見るため息とともにロマンチックな遠い目をする白葉教授の肩を三宅教授が悪意を込めて力いっぱいどついた。
「うははははは。ワシに任せろ! 宇宙へいくためのテクニックなら、すでにこの手のうちにある!」
「後は、宇宙に居座り続ける技術が必要ってわけか。ま、金が続いている内に、とっとと宇宙に居座るための布石って奴を整えちまおうや」
「どうにかなりますかなぁ」
「どうにかなるのではない。どうにかするのだ! うは。うはははははははは!!」
両腕を腰にあて、胸をぐいと張って腹の底から「うはは」と笑い続ける三宅教授はともかく、金居教授は白葉教授の小さなため息に気づいた。
「どうした、白葉君。なんだか元気がないじゃないか。何か心配ごとかね?」
「いやあ……去年の暮れにまたひとつ失敗をやらかしまして……」
「女子学生に手でもつけたのかね」
「いい歳こいて、金居さんじゃあるまいし……。ウチで雑木林を作ってるんですが、林の中の保湿のために蔦をね、作ったんですな。とびきり繁殖力旺盛な奴。ただ、繁殖した場所が、高温高湿度のなんというかこう……えーっとね、雑木林の保湿どころか南の島の密林みたいになってしまうような代物で、およそ役に立たない代物なんですが……これが、こぼれちゃいましてね。厳重に管理しておいたはずなんだが、種子のサンプルが足りんのですな」
「つまり、またしてもバイオハザード騒ぎを起こしかけたわけだな。うんうん、そんなこと大したことじゃない。だいたい、まだそれは誰にも知られておらん上に、それで問題が起きているわけじゃないんだろう? ようは、失敗作が人目につかなければいいわけだ。生物工学研なんか、失敗した改造生物は闇から闇へ処分しとるもんね。21号島あたりとか、黙って処分してしまえばわかるまい」
「それって、廃棄物処理法にひっかかりませんか?」
「白葉君。些細なことを気にしていると、禿げるぞ。科学の進歩には多大な犠牲が必要なときもある。そうした犠牲や失敗の上に、我々の目指すべき輝かしい未来が築かれていくのだ」
三宅教授は自衛隊隊員募集ポスターのように凛々しく立ち上がると、窓の外に燦然と輝く太陽を指さして再び「うはは」と笑った。
子供時代をアニメとSFとファンタジーな趣味に投じた世代である40〜50歳代の、こうした趣味の職人的マッド・サイエンティストたちによって、現代の科学技術が日夜進歩を遂げているとは、よもや誰も思うまい。
しかし彼らは、社会の中心的年代となった今も「ある趣味にすべてを投じて打ち込む」という30数年前の時代に培った独特の気質を、決して捨て去ってはいなかったのである。さらにもう20歳も上のすでに老境に達しつつある世代は、未だに学生運動と聞くと心躍ってしまう。
誰しも、青春時代に培った感覚は、一生ついてまわるものらしい。
中年から熟年に達しつつある人々にとって、依然、科学・技術は「趣味」の領域なのであった。
「は? ……あの、どういった御用件でしょ?」
「あの、あたし鵜飼さんの友人で、鵜飼さんから大事な話を言付かってきましたので……」
平山恭子と名乗った女性は、鵜飼クーミンの名を出した。メッセンジャーではなさそうだが……。
「鵜飼ちゃんから? なんだろう……まぁ、いっか。散らかってるけど、上がってください」
根戸は、居間に散らかっていた皿やコップと、床に転がっていた飛鳥龍児を手早く片付けた。男の一人暮しに似つかわしく、フローリング張り床暖房の居間には飾り気めいたものもない。
「で、大事な話というのは……?」
「根戸さん、あなたの知っている重大な情報というのを、教えてください」
「……はいぃ?」
恭子は単刀直入だった。
「いえ、だからあなたの知っている群島に関する情報というのを、わたしに教えてください」
「……うーん。なんだか、最近は危ないことに首を突っ込みたがる人が多くて困るな。飛鳥君。これは僕の知らない何かの流行か何かかい?」
「はぐらかさないで! あなたの恋人が、あなたのこと心配してくれているのよ!」
「誰だって?」
「あなたの恋人よ」
「誰が?」
「……鵜飼さん」
「恋人?」
「……」
「そうなんですか? 根戸さん」
「いや、僕も初耳なんだが……」
どうやら、誰一人として状況が理解できている者がいないようだ。
根戸は混乱を避けようと、メモを作り始めた。
「ちょっと、ちょっと待ってくれ。あまりに唐突すぎて、前後の経緯がよくつかめなかった。質問をもう一度頼みます。誰がどうして僕の情報を知りたがっているんだって?」
口ごもる恭子の言葉を飛鳥が継いだ。
「つまりこういうことですか、お嬢さん。根戸さんの恋人の鵜飼さんが、根戸さんのことを心配して、根戸さんのために、根戸さんの知っている情報を知りたがっている」
「そ、そうです」
「なんで?」
根戸宏は、自分あての質問の意味がまだよく理解できていないようだった。
「あなたの身の安全のためでしょう?」
「いや、質問の意味がよくわからなくて……」
腕を組んでうーむとばかりに考え込んでいるポーズをとってみせる根戸にいらだちを感じたか、恭子は再び質問の意図を繰り返した。
「あなたが知っている何かの情報を、鵜飼さんが知らないと、あなたが危険になるからでしょう? そのためにわざわざ、探偵まで雇って……」
「君は探偵なのか?」
「い、いえ……あの、わたしは……」
「この質問には明確な嘘がひとつと、よく理解できない意図がひとつある。まずは、鵜飼ちゃんは僕の恋人ではない、ということ」
「本当に違うんですかぁ、根戸さん」
「飛鳥君。君は僕を芸能番組の担当に売るつもりかい? 少なくともこれまでの過去においてはそういう噂も関係もいっさいない。で、それはまあよしとしよう。もしかしたら僕が知らなかっただけで、鵜飼ちゃんが僕の事を秘かに思っていてくれたのかもしれん」
「自分で言ってて恥ずかしくなりませんか」
「うーん、ちと恥ずかしい。では、もうひとつの疑問。僕が持っている情報が僕を危険にしているのは、事実だ。去年も何度か事故に巻き込まれたし、部屋の中を誰かに荒されたこともあるし、ASの廊下でさりげない忠告っていうのを受けたこともある。
だが、僕が知っている情報が何なのかを、僕以外の人が知ったとして、僕の身が安全になるという保障はどこにもない。むしろ、ある情報を知っているからこそ僕の身の安全は保証されているわけで、誰かに漏らした瞬間から僕はもう用済みということになって、命を危険に晒すどころか、いきなり命を奪われてしまう可能性もあるわけだね。とすると、僕の知っている情報を知りたがっている人物にとって、僕の身の安全というのは最初から考慮の外にあるわけだ。
だいたい、もし鵜飼ちゃんが僕の情報を知りたがっているのだとしたら、直接聞くよあの人は。 ON AIR中にね。だって、情報を持っている人間、伝える人間にとって、それがいちばん安全な方法だから。
秘かに聞き出す必要があるのは、僕から聞き出した情報を、僕を含めて他の誰かに知られたくない、その情報を専有したいという何かの意志があるからだろうね。
ここで、ではそれが誰の意志であるか、が重要になってくるわけだが……」
根戸は、すっかり小さくなってしまった恭子をなだめるように言った。
「いきなり単刀直入に切り込まれたんで、すっかりうろたえてしまったけど、君はプロの探偵ではないよね?」
恭子は黙って小さくうなずいた。
「鵜飼ちゃんと僕が恋人同士で、鵜飼ちゃんが僕の心配をしているって誰か聞かされて、それを信じ込んできたんだよね。心配してくれてありがとう。でもこれってけっこう危ないことだろう。僕にも鵜飼ちゃんにも縁のなさそうな人に思えるけど、どうして他人事でそこまでしようとしたか……これは、僕や鵜飼ちゃんがという問題じゃないな。なぜ君がここまで来たのかと言えば、一つには内緒の話に興味があったから。しかし、これを頼んだ誰かに君は特別な感情を持っていたりしたからなんじゃない?」
「つまり、断われないような人物に頼まれて、うまく利用されたとか?」
恭子は握りしめた拳の上に、ぽたりと雫を落とした。
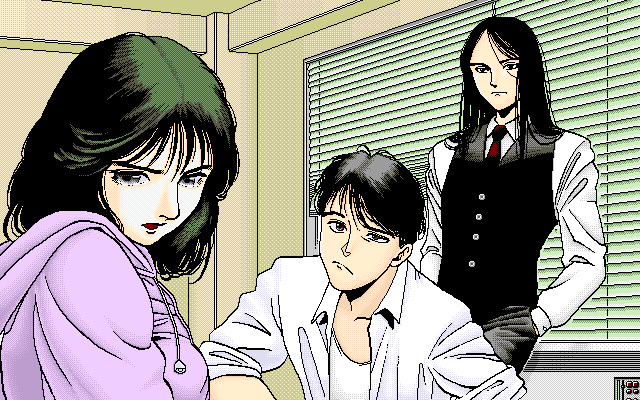
「わたし……特別な感情なんか……もってません! だってあんな奴、わたしとは全然関係ないもの。だって、たった2回しかあったことないし、そのくせ妙に期待を持たせるような気障なことばっかり言って……話を聞かされた後、確かに自分からこの役を買ってでたわ。報酬の話なんか何もない。ただ、何かしなきゃいけないような気になって……それに、それにほんの一瞬だったけど、自分がスリルに満ちた冒険に飛び込むヒロインみたいに思えて……わたし、わたし自分の姿に酔いしれていたのかもしれない。ただ、わたしが一方的に思い込んでいただけなのかも……」
恭子は胸につけていたブローチを引き剥すと、部屋の隅に放り投げた。
飛鳥は薔薇をあしらった小さなブローチを拾い上げた。
「恋人?」
「違います! あんな人、あたしの趣味じゃないもの! 絶対に恋人なんかじゃないわ!」
「そ。そいじゃこれは、こうだっ☆」
二階の窓をあけると、すぐ下に運河が見えた。飛鳥は恭子のブローチを運河に向かって放り投げた。わずかに距離が足りず、ブローチは運河の手前にある遊歩道に落ちて見えなくなった。
飛鳥はポケットをまさぐると、比較的綺麗なバンダナをひっぱりだして恭子に渡した。
「しかし、ルフィー西石ですかー……」
「日本国内じゃ母方の姓を名乗ってはいるけど、彼の実家はロイズ保険協会のアンダーライターに名を連ねるほどの資産家にして名家だよね。そのファミリーの一員であるルフィーが、少々知りすぎている所がないこともないとはいえ、一民間人にすぎない僕を追い回すのはなぜか。飛鳥君、君の考えは?」
「ええと、ルフィーの依頼人=ルフィーの一族の秘密を知っているから口封じのため……だったら、さっさと根戸さんを殺せば済むことですね。そいじゃ、彼らの知らないことを知っている、もしくは知っていると思われているから。またはそれを探るため。不幸にもさっきの女の子はその謀略に巻き込まれた」
「まぁ、命が絡まなくて何よりだったけどね。思うに、東京人工群島=バイオスフィア計画に金を出しているのは、東京都や日本の企業なんかだけじゃなく、ECやアメリカの企業なんかじゃないのかなぁ。日本に研究者と研究資金を集中させて一気にブレイク・スルーをさせておいて、後から外圧をかけて技術に便乗しようって腹じゃない? ルフィーの一族も結構な資産家だし、それらのシンジケートのひとつなんじゃないだろうか。
複合企業体としての日本を、アメリカとECにある資本が利用しようとしているって感じ、かな。国家というのは企業……昔風に言えば豪商……があってこそ成り立つ形態であり、国家の存亡は常に企業に左右されてきた。たぶん、これからもね。
まぁ、ボーダーレスの時代と呼ばれて久しいわけで、それぞれの企業は、これまでは金を稼ぐのに自分の本社のおいてある国家を利用してきたけれども、最近では特定の国家・政府を利用するだけじゃなく、複数の国家を共同利用して儲けようという、国際的な時代になってきた、ということだろう」
「なんせ、日本は資本運用がずるがしこい上に、治安も世界的にはマシなほうですからねぇ」
「僕らが気づかなかっただけで、当の昔から金儲けをする奴らはそういう方法でうまくやってきたのかもしれないがね。そういう風にみんなが仲良く日本を使うのはいいとして、金を出すからには、現状を総て押さえておきたいのが人情ってもんだよね」
「そうですねぇ。自分が投資したものに、少しでも不明瞭なところがあると、気持ち悪いですもんね」
「さて。僕がここ最近、再三繰り返し連呼しているのはなんだったかな?」
「東京ガラパゴスを探検する、でしたっけね」
「では聞くが、東京ガラパゴス……21号埋立地って、いったいなんなんだ。あれは東京人工群島の計画の中に入っていることなのかな? 群島の整備が始まったのが、2000年初頭として、すべての埋立地はそれぞれの計画スケジュールにそって開発が進められてるのに、21号埋立地はもう10年以上も放置されたままだ。
バイオスフィア絡みで誰かが意図して放置しているものなんだろうか。でも、なんのために? 今じゃ、不法投棄の対象にさえなりかかってる。
これって、どうみてもおかしい。
たぶん21号埋立地というのは、バイオスフィアと東京人工群島に出資した人々のスケジュールの中には入っていないんじゃないかな。だから、戸惑っているんだ。解らないままになっている答えを知りたくて。彼らも21号について興味津々なのさ。僕が去年、大々的に『21号を探検する』ってぶちあげただろう。だから、早速それに食いついてきた」
「根戸さん。これって僕の推測ですけど……もしかして、根戸さんだけが知っている情報なんて、最初からなかったんじゃありませんか? 『情報をもってるぞ』というフリをすれば、それにお茶の間以上に興味を抱いている奴らが接触してくると見越して、彼らに自分に手を出させるためだけに、秘密を持ってるフリをしてきた」
「ぴんぽーん。半分当たり。うんうん、いいねぇ。だんだん鋭くなってきたよ、飛鳥君。これなら僕にもしものことがあっても、大丈夫だよね。
確かに僕は明確な情報とか秘密というのは持ってない。持っているフリをしてみせたのも事実だ。だがね、答えはあの島の中にあると思ってる。誰も現地を調べていないから、何とも言えないわけだがね」
「……でも、東京湾の中にある、たかだか一個の島を誰も調べられないのってのは変ですよね。『彼ら』だって、とうに21号は調べたんじゃないですか。そして利用しようとしてきたはずでしょう」
「でも、答えが見つからなかったか、利用しようとしてもできなかったか、誰も帰ってこなかったのか。ひとつ、それを現地で調べてみようじゃないか。
いろいろアクシデントが続いたが、準備は整った。これでやっと『東京ガラパゴス』に挑めるというわけだね」
「そしてあくまでも、表向きは『秘境探検モノ』として、行動するわけですね? この目的を覆い隠すために」
「よし、合格!」
ジャーナリストの使命は、嗅ぎつけた謎をそのままふりまくことではない。情報の群れを観察し、キーワードから連想し、答えを引き当て、それを立証するまでは深く静かに待つ。確かな答えが得られるまでの間、真実を虚偽の毛布に覆い隠してその時を待つことが重要なのだ。